失敗しないLANケーブルの選び方のポイントと新築時のLAN配線を解説
2025年05月08日 更新日:2025年05月08日
LANケーブルはインターネットに有線で接続するために必要なものですが、どのようなものを選べば良いのか分からない方もいるのではないでしょうか。
本記事ではLANケーブルの基礎知識をはじめ、失敗しないLANケーブルの選び方を解説します。戸建ての新築時に失敗しないLAN配管とLANケーブルの選び方にも焦点を当てるので、ぜひ参考にしてください。
LANケーブルとは?基礎知識を解説

ここでは、LANケーブルとはどのようなものかの基礎知識から、LANケーブルの国際規格や特徴までを解説します。
LANケーブルとは
LANケーブルとは、有線でインターネットに接続する際に使うケーブルのことです。LAN(ラン)はローカルエリアネットワーク(Local Area Network)の略称であり、同じ建物やフロア内など、比較的限られた範囲内にある機器同士をつなぐネットワークです。
ルーターやネットワークハブなどの機器と、パソコンやゲーム機といった端末を有線でつなぎ、データのやり取りをするために使われます。
LANケーブルの国際規格
LANケーブルの仕様には、国際規格があります。国際規格を定めているのはIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)です。IEEEは電気・電子・通信・コンピュータ等の分野における、世界最大規模の専門家組織団体です。
「IEEE802委員会」はIEEEの委員会の一つで、1980年2月に発足したことが名称の由来です。LAN標準化のために設置され、委員会の3番目の作業グループである「IEEE 802.3委員会」が、現在標準的な通信規格として普及しているイーサネットを担当しています。
IEEEが策定する標準規格は世界各国で採用されており、有線LANの規格「IEEE 802.3」以外にも無線LANの規格「IEEE 802.11」などが挙げられます。
LANケーブルの特徴
一般的なLANケーブルには、両端に「RJ45」という四角いコネクタが付属しています。このコネクタには8本の銅線が使用されており、2本ずつより合わせた構造になっています。また、コネクタにはツメが付いており、これがLANケーブルの抜け落ちを防ぐ役割を果たしています。
LANケーブルは規格によって通信速度などが異なるため、利用環境に合ったものを選びましょう。選び方については、後ほど詳しく解説します。
LANケーブルを使うメリット・デメリット
昨今は公共の場でも自宅でもWi-Fi(無線接続)の普及が進んでいることもあり、LANケーブルの利用シーンは減少しています。
しかし、有線接続(LANケーブル)と無線接続(Wi-Fi)には、それぞれメリットとデメリットがあり、使用目的や利用環境に応じてどちらの接続方法が適しているのか異なります。双方のメリット・デメリットをここで理解しておきましょう。
無線接続と比較した際のLANケーブルを使うメリット
LANケーブルを使用するメリットの一つは、高速かつ安定した通信が可能となることです。
無線接続の場合、ルーターやパソコン、ゲーム機の間に障害物があったり、距離が遠かったりすると、「つながりにくい」「不安定になる」「速度が遅い」などの問題が起こりやすいです。
一方、有線接続なら物理的に機器をつなぐため、安定した通信速度で利用できます。そのため、リモートワークやオンライン授業、オンラインゲーム、動画視聴など、安定したネット環境が必要な場面ではLANケーブルを使った接続がおすすめです。
また、有線接続はケーブルを直接確認できるため、接続がうまくいかない際に原因を見つけやすい点もメリットの一つです。
新築戸建てやマンションにおいて、違うフロアや複数の部屋でインターネットを使う場合、無線LANでは電波が届きにくいケースが少なくありません。速度が落ちたり接続が切れてしまったりする原因となるので、インターネットを快適に楽しむには、各部屋に有線LANケーブルを張り巡らせられるよう、LAN配線工事を行うのがおすすめです。
LANケーブルを使うデメリットと注意点
LANケーブルを利用した有線接続には、パソコンやゲーム機などの機器にLANポート(LANケーブルの差し込み口)が必要です。しかし、現在はWi-Fiの普及により、LANポートが搭載されていない機器が増えています。そのため有線接続を考えている場合は、機器にLANポートがあるかを確認しましょう。LANポートがない場合、USBポート(USBケーブルの差し込み口)があれば、それらをLANポートへ変換するためのアダプターを用いることで、有線接続が可能になります。ただし、USBポートの規格によっては、アダプターを利用しても有線接続ができない可能性があるので注意が必要です。
また、有線接続をする場合はケーブルが邪魔にならないよう、配置の計画をしっかりと立てる必要があります。新築やリフォーム、リノベーションの際は、LAN配管が必要な場所と避けた方が良い場所をきちんと把握しておきましょう。
LANケーブルには劣化リスクもあります。LANケーブルの寿命は、およそ20年といわれています。劣化したLANケーブルを使い続けると、ネットワーク障害や感電・発火の原因となる可能性があるので注意が必要です。
失敗しないLANケーブルの選び方

LANケーブルは、家電量販店やコンビニ、100円ショップなどさまざまな場所で購入できますが、種類が多いためどれを選べば良いのか迷う方もいるでしょう。
LANケーブルは規格によって速度が異なるため、選択を誤ってしまい後から後悔する方もいます。
環境に合うLANケーブルを選ぶには、カテゴリとタイプ、長さ、構造の4つのポイントを押さえることがポイントです。詳しくはこれから解説するので、ぜひ参考にしてください。
(1)LANケーブルの「カテゴリ」は6A
LANケーブルの性能や特徴は、「カテゴリ」と呼ばれる規格で区分されています。細かな違いはあるものの、重要視すべき違いは通信速度であり、接続する機器の最大通信速度に対応したカテゴリの製品を選ぶことが大切です。
LANケーブルには下位互換性があるため、接続する機器の通信速度が不明な場合は「カテゴリ6A」を選ぶと良いでしょう。詳しくは下記にて紹介します。
LANケーブルのカテゴリとは
カテゴリとは、性能や特徴によって区分されている規格で、主に通信速度に影響しています。2025年4月時点で販売されているLANケーブルは、カテゴリ5~8までの規格に分かれています。
| カテゴリ | 通信速度 | 伝送帯域 |
|---|---|---|
| カテゴリ5 | 100Mbps | 100MHz |
| カテゴリ5e | 1Gbps | |
| カテゴリ6 | 250MHz | |
| カテゴリ6A | 10Gbps | 500MHz |
| カテゴリ7 | 600MHz | |
| カテゴリ7A | 1000MHz | |
| カテゴリ8 | 40Gbps | 2000MHz |
数字が大きくなるほど、通信速度や伝送速度が速いです。
自宅の回線の最大通信速度で判断
最適なカテゴリのLANケーブルを選ぶには、自宅の回線の最大通信速度で判断しましょう。例えば、1Gbpsに対応している自宅の光回線であれば、最大通信速度は1Gbps以上の、カテゴリ5e以上のLANケーブルを使用するのがおすすめです。10Gbpsの速度を利用する場合は、カテゴリ6A以上のLANケーブルを選んでください。
今後は1Gbpsを超える高速通信が普及し、10Gbpsネットワークが標準になるといわれています。そのため、一般家庭では「カテゴリ6A」を採用すると良いでしょう。
「カテゴリ6A」や「カテゴリ7」以上の一部のLANケーブルは業務用の「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」で、電磁波の影響を防ぐシールド処理が施されています。そのため、STPケーブルはネットワーク機器に接地(アース処理)が必要であり、アースがない環境ではノイズの影響で通信速度が遅くなる場合があります。従って、一般家庭ではシールド処理がされていない「UTP (Unshielded Twisted Pair)ケーブル」を選びましょう。
LANケーブルのカテゴリ確認方法
LANケーブルのカテゴリを確認するには、以下の方法があります。
- ケーブルに印字されている「カテゴリ」表示を確認する
- ケーブルに印字されている「配線規格名」を確認する
ケーブルにカテゴリが印字されている場合は、すぐに確認可能です。一方、ケーブルによっては「配線規格名」が印字されているものもあります。
配線規格名が印字されている場合でも、規格名からカテゴリの判別ができます。規格名は更新されるので、見当たらない場合は最新の情報をインターネット検索で確認しましょう。
(2)LANケーブルの「タイプ」はストレート

LANケーブルは「タイプ」でも分かれており、「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があります。
ストレートケーブルは、パソコンとハブ・ルーターなど他の機器を接続するために使用します。クロスケーブルは、パソコン同士を接続したい場合に使用するケースが一般的です。
現在は、自動判別機能(AutoMDI/MDI-X)が搭載されている機器が増えたため、基本的にストレートケーブルのみで対応可能です。古い機器や特殊な機器を使う場合は、ストレートケーブルとクロスケーブルを使い分ける必要があるので、機器のマニュアルで確認をしましょう。
(3)LANケーブルの「長さ」

LANケーブルを選ぶときは「長さ」も重要なポイントです。ケーブルの長さが短すぎると機器同士の接続ができず、長すぎるとノイズによる通信速度低下や取り回しの際に不便さが生じます。ケーブルが長いと信号が減衰し、安定した伝送が難しくなる可能性があるので注意が必要です。
LANケーブルの長さは、1mから100mまであります。自宅で使用する場合は、1~3m程度の長さが一般的です。部屋の広さやレイアウト、接続機器の位置に合わせて、最適な長さを選びましょう。
(4)LANケーブルの「構造」(単線とより線)

LANケーブルは「構造」にも違いがあり、芯線には「単線」と「より線」の2種類があります。各特徴を理解し、用途に応じて選ぶことがポイントです。
単線は8芯がそれぞれ1本の太い銅線で構成されており、長距離の伝送に向いている点が特徴です。より線は各芯が7本の細く柔らかい銅線で構成されていて、短距離の伝送に向いています。
ケーブル長10m以上の環境で利用する場合は、丈夫でノイズに強く、安定した通信ができる「単線」が適しています。ケーブル長が5m未満なら、狭い場所でも柔らかい銅線で配線がしやすい「より線」が良いでしょう。
LANケーブルの機能やスペック
ここからは、LANケーブルを選ぶ際に役立つ、機能やスペックの詳細を解説します。
LANケーブルには柔軟性に富み、曲げやすく取り回しがしやすい極細ケーブル(スリムタイプ)、屋外で使用できるように設計されている屋外向けのLANケーブル、音質の向上をうたうオーディオ用ケーブルなど、多種多様な種類があります。
用途に適した製品を選ぶために、ぜひ参考にしてください。
フラットケーブル

フラットケーブルは厚さ1mm程度の薄さで、平らな形状をしているLANケーブルです。通常のケーブルよりも非常に薄いので、部屋の美観を損ねることなく配線ができる点が魅力です。
カーペットやジョイントマットの下などにも通すことが可能で、床や壁沿い、ドアの隙間を通して部屋を跨いだ配線もできます。通常のLANケーブルに比べると、引っ張られた際の強度が劣ることが弱点です。
巻き取り式

巻き取り式のLANケーブルは、LANケーブルの両端を引っ張ることでケーブルの引き出しや収納が可能です。
スピーディーにケーブルを引き出したり収納できたりするため、持ち運びに便利なアイテムです。出先やホテルなどで有線接続する場合などに活躍するでしょう。
コネクタ保護機能付き

コネクタ保護機能付きのLANケーブルは、LANポートとケーブルのコネクタを固定する「ラッチ」に耐久性の高い素材を使用している点が特徴の、ツメ折れ防止プロテクタを採用した製品です。
頻繁にLANケーブルの抜き差しをするなら、コネクタ保護機能付きのLANケーブルをおすすめします。
PoE対応
「PoE」とは「Power over Ethernet」の略で、コンセントからではなくLANケーブルによって給電するシステムを指します。PoEを利用するには、PoE対応のLANケーブルの他に、PoE対応のルーターを用意する必要があります。
LANケーブル1本でネットワーク機器への電力供給・通信ができるため、省スペース配線可能な点が強みです。
新築のLAN配線で失敗しないためのポイント
「新築の際にLAN配線工事をしておけば良かった」と後悔する方は意外と多いです。壁や外壁を這わせたり、壁の中にケーブルを通したりするのは専門知識がないと難しいので、できれば新築時に業者へ依頼し、対応してもらうのがおすすめです。
ここからは、戸建ての新築時に後悔しないためのLAN配管のポイントを解説します。なお、TOKAIケーブルネットワークでは、新築時に光回線を導入した際に割引が適用されるお得なキャンペーンを展開しています。ぜひこちらから特典についてお問い合わせしてみてください。
Wi-FiルーターやLANケーブルの差し込み口の設置場所を決める
新築のLAN配線の計画をする際は、Wi-FiルーターやLANケーブルの差し込み口をどこに設置するか決めておきましょう。Wi-Fiルーターを適切な場所に置かないと、電波が届きにくくなってしまう可能性があります。
Wi-Fiルーターの設置場所は、部屋の中心の床から約1m離れた高さが良いです。LANケーブルの差し込み口は、Wi-Fiルーターの近くに設置するのが一般的です。設置が難しい場合は、あらかじめ壁内に配線を通しておきましょう。
必要な場所にLAN配管を設置する
新築に住み始めてから後悔しやすい点に、LAN配管の設置場所があります。新築の際は、全部屋に配管を行うことが後悔しないポイントです。
予算的に難しく全部屋への設置が困難な場合は、リビング、寝室や書斎、子ども部屋の3カ所には配管することをおすすめします。
2階にもLAN配管を設置する
LAN配管が1階のリビングのみの場合、2階にある書斎までWi-Fiが届かないといった事態が起こります。その結果、リモートワークなどで2階の部屋でインターネットを使いたくても、LANケーブルが届かないといったトラブルにつながります。
このような事態を避けるには、1階だけでなく2階でも有線LANを使えるようにすることが必要です。光回線ならではの速度を生かすためには、2階に直接有線回線を引き込む方法がベストです。
LAN配管を避ける場所も把握しておく
テレビや電子レンジ、冷蔵庫の近くにLAN配管を配置すると、シールド処理が施されていないLANケーブル(UTPケーブル)では電磁波の影響を受け、通信速度が遅くなる可能性があります。そのため、LAN配管をする際は、避けるべき場所もしっかり把握しておくことが重要です。
また、家電だけでなく、水回りは漏電を引き起こす恐れがあるので配管を避けましょう。
空配管を配置する
「空配管」は、配管の中が「空(から)」なので「空配管(からはいかん)」と呼ばれます。中にLANケーブルや電話線などを通せば簡単に配線できるように、壁や天井などに通しておく配管を指します。
空配管がない場合、後から有線接続をしたくなったときは室内に配線が必要です。モールで配線を隠すこともできますが、見栄えが悪くなるため、空配管の設置がおすすめです。
建売住宅の場合、各フロア1カ所ずつしか空配管がない場合もあります。注文住宅を建てるのであれば、美観を損なわないように全部屋への配管をおすすめします。
2階までLANケーブルを配線する方法
戸建ての2階に光ファイバーケーブル光回線を引き込むための工事は、いくつかの条件があります。家の建て方によっては工事ができないケースがありますが、その場合は長いLANケーブルを配線することで解決できるかもしれません。
ここでは、2階までLANケーブルを配線する際のケーブルの選び方や、つなげる際の注意点を解説します。
長いLANケーブルの選び方
10m以上の長さのケーブルなら、ノイズに強くて安定した通信ができる丈夫な単線タイプのLANケーブルを選びましょう。
形状は、一般的なスタンダードケーブルがおすすめです。薄くて平らな形状のフラットケーブルは隙間に通せたり、外観を損ねなかったりなどのメリットがありますが、ノイズに弱いので長い距離での利用は適していません。
LANケーブルを2階までつなげる際の注意点
LANケーブルは、使用する環境と目的に合わせて適切な長さを選定することが重要です。必要な部屋までの距離を計測した上で購入しましょう。ギリギリの長さではなく、余裕のある長さのものを買うのがおすすめです。
LANケーブルをつなげるときは、ルーター側から配線することがポイントです。出入り口では、ドアの上部に這わせるように配線すると、ドアの開閉時に邪魔になりません。
まとめ
Wi-Fiが普及している一方で、有線接続には通信速度が安定するなどのメリットがあります。ただし、LANケーブルを間違って選ぶと、回線の速度を十分に生かせなかったり、ケーブルが邪魔になったりすることがあります。そのため、目的や環境に合ったLANケーブルをしっかり選ぶことが重要です。
また、LAN配管の設置場所は、新築に住み始めてから後悔するケースもあるため、事前にしっかりと計画を立てましょう。
TOKAIケーブルネットワークでは、新築時に光回線を導入した際に割引が適用されるお得なキャンペーンを展開しています。ぜひこちらから特典についてお問い合わせしてみてください。

2025年05月09日
お役立ち情報
2025年05月09日
お役立ち情報





 サービスのご案内
サービスのご案内 おトクな情報
おトクな情報 料金案内
料金案内 よくあるご質問
よくあるご質問




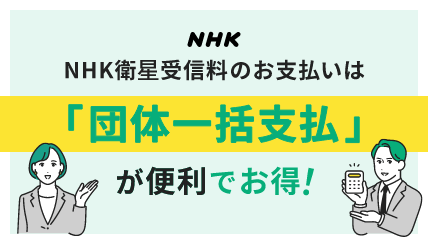














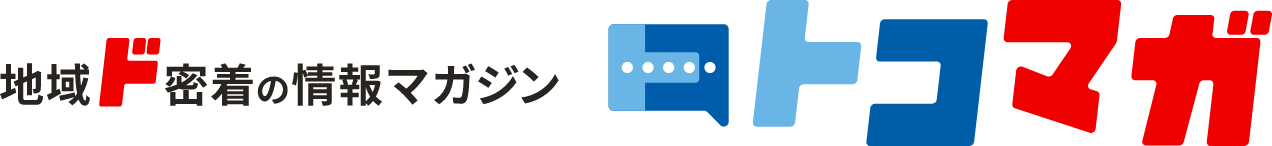
 シェアする
シェアする
 シェアする
シェアする
 シェアする
シェアする



